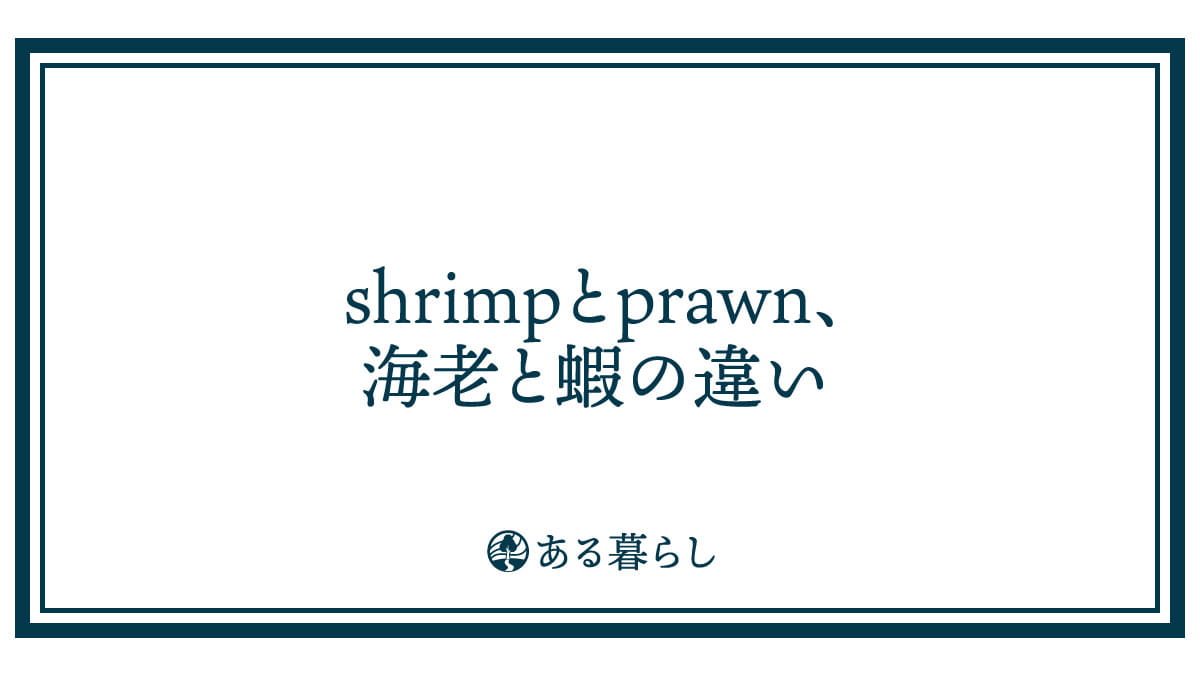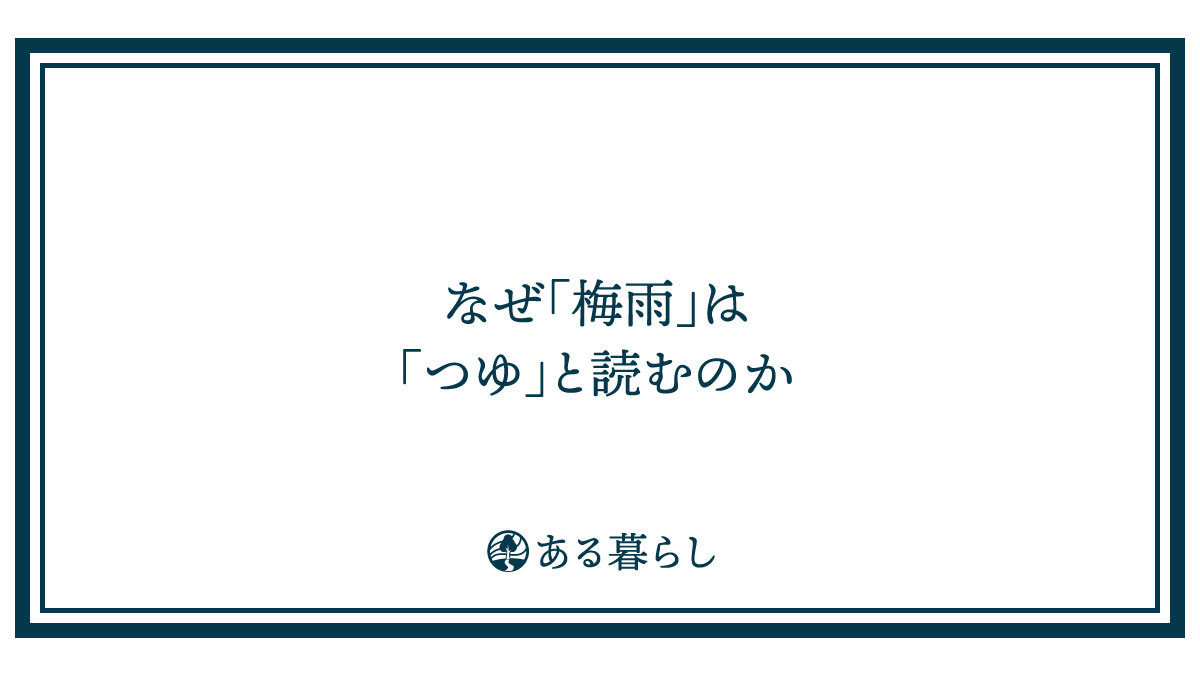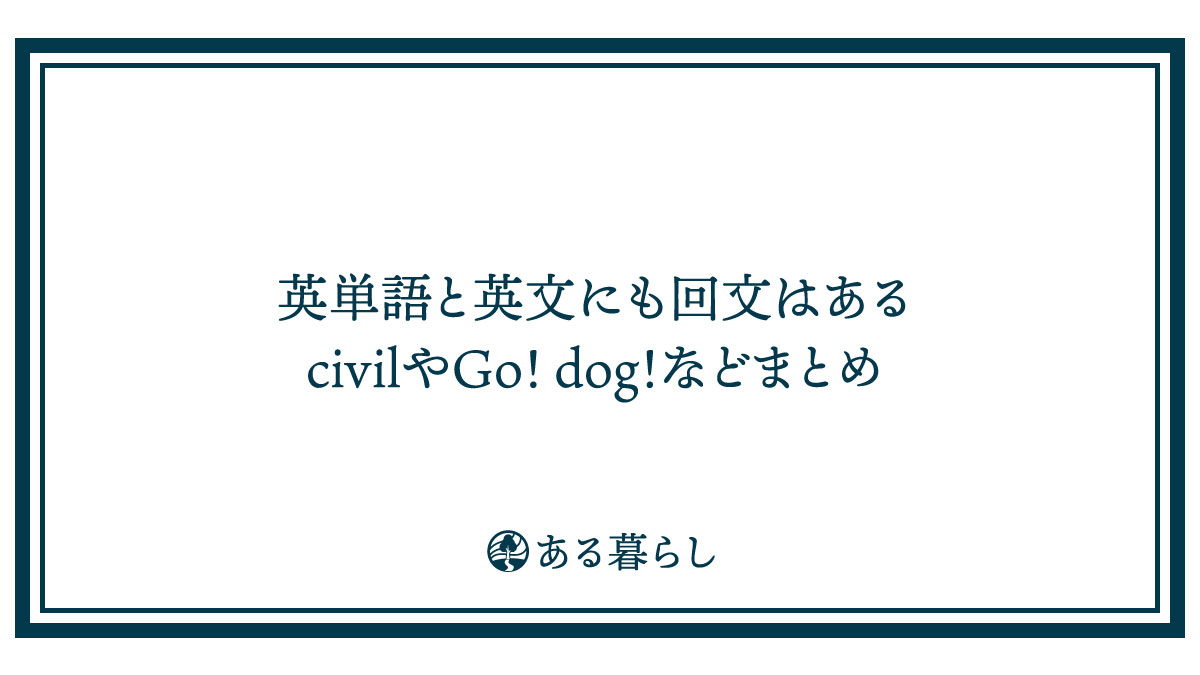スポンサーリンク
今回は日々のちょっとした疑問を調べてまとめてみました。
「エビ」を漢字で書くとき「海老」と書かれているのをよく見ますがなかには「蝦」と書くことがあります。この2つの違い何なんでしょう。
また同じエビなのですが、英語で書くと「Shripm シュリンプ」と「Prawn プラウン」と書くことがありますが、ShripmとPrawnに違いはあるのでしょうか。
調べてみると意外と面白いことがわかりました。
勝手なShrimpとPrawnの違いのイメージ
まずは僕自身の勝手な「Shrimp シュリンプ」と「Prawn プラウン」の違いのイメージから書いていきます。
僕のイメージではShrimpよりもPrawnの方が大きい印象があります。
というのも外食をしてメニューに「Prawn Tempura」と書いてあれば、それは大きなエビの天ぷらを想像できます。ところが「Shrimp Tempura」と書かれてたら「小エビのかき揚げ」を思い浮かべます。
これは僕の勝手なイメージです。では、そんな勝手なイメージが正しいのか調べていきましょう。
スポンサーリンク
いろんな話の前に、一言だけ
ちょっと余談です。
この記事を書くためにエビについていろいろ調べました。そのなかで知ったんですけど、エビは「昆虫の仲間」という説があるそうです。
もともとエビも昆虫も節足動物という意味では同じ生き物でした。
進化の過程で海で生活するようになったものがエビ。そして陸地で生息するようになったのが昆虫だとか。
そのため今注目されている「昆虫食」で「コオロギを多くの人が食べれれるように」と研究・開発している人たちが解決しようとしているのが「コオロギはエビやカニと同じアレルゲンを含むこと」です。
エビ・カニなど甲殻アレルギーの人はコオロギを食べるとアレルギー反応がでるそうです。
つまり「エビが食べれるなら虫も食べれるはず」なんですね。
ところが採れたてピッチピチのエビが中華鍋で炒められていたらヨダレが出るのに、同じ節足動物のバッタがピッチピチの状態で中華料理で炒められていても「気持ち悪い!」ってなる人多いというのも事実です。
個人的には母方の実家がイナゴとか蜂の子を食べる地域に住んでいたため、小さい頃よく食べる機会がありました。そのせいもあって虫を食べることにまったく抵抗がありません。むしろ「美味しそう」と思ってしまうほどです(笑
余談の余談なのですが、ダンゴムシはそもそも昆虫でいって知ってました?
海で見かけるフナムシやワラジムシの仲間で、大本を辿っていくとエビや蟹と同じ分類に入るそうです。これも意外。
さて話がそれましたがShrimpとPrawn。それとついでに漢字の海老と蝦の違いに話を戻しましょう。
スポンサーリンク
英和と英英辞書でPrawnとShrimpの違いを調べる
まず英語のShrimpとPrawnの違いを英和辞書で調べてみると
- Shrimpは、「食用の小エビ」もしくは「チビ」「取るに足らない人(もの)」
- Prawnは、エビ。中型エビの総称
という意味があるそうです。Shrimpには「取るに足らない人」「チビ」なんていう意味もあるんですね。面白いです。
さらに英英辞書で調べると
- Shrimp is a small free-swimming crustacean with an elongated body. typically marine and frequently of commercial importance as food.
, is someone who is very small, used humorously. - Prawn is a marine crustacean which resembles a large shrimp.
となってました。
英和辞典だと「PrawnはShrimpより大きい」という記載があるので、何となく自分が抱いていたイメージは合っていたのかな?という気がします。
イギリス英語とアメリカ英語でも違う
スポンサーリンク
他にも動物学的な違いとは別で、一般的にどう考えられているか?をみていったときにイギリス英語とアメリカ英語で若干異なるようです。

こんな感じです。
イギリス英語では両方の総称がPrawn。アメリカ英語ではShrimpが総称みたいです。なんだかムズカシイですね…。
とはいえ、これも英語のグローバル化が進んでいるため、イギリスにいる人でも「大きなエビがShrimp」と思っていたり、そのまた反対があるかもしれません。
もう少し違いを掘り下げてみる
もう少し掘り下げてみました。ただ「生物学上の違い」という側面が強くなってくるので、ちょっと小難しい話になってしまいました。ちょっと読んでみて「ここはどうでもいい」という場合はここをスキップしてもOKです。
まず、ShrimpとPrawnは両方とも十脚類と呼ばれる生き物で脚が10本あります。
ところが生物学的に更に分類していくと、Shrimpは「エビ亜科」と呼ばれるところの属し、Prawnは根鰓亜目(こんさいあもく)と呼ばれるところに属しています。
外見の違いはいくつかあるんですけど、正直なところそれらを全部聞いたあと「うん。その違いどうでもいいかも」と言いたくなるようなことが多かったです。
ここでは「ザックリ」とShrimpとPrawnの違いをまとめてみると
スポンサーリンク
- 殻の構造が違う
- ハサミがPrawnは左右に3本ずつ6本、Shrimpは左右2本ずつ4本ある
- エラの構造が違う
- 卵を産むとPrawnは海中に放流する。Shrimpは卵を抱える
大体こんな感じです。どうですか?だいぶ生物学的な話ですよね。
そして生息する場所にも違いがあります。
- Shrimpは主に海水に
- Prawnは海水でも生息しているが真水にも生息している
とのことです。
結局PrawnとShrimpの違いは何?
学術的にはハッキリ違うShrimpとPrawnなんですけど、実際食べる人たちにはわからない違いばかりでした。
一般の人が気にする一番のポイントは大きさですね。
大きさで並べると「Prawn > Shrimp」の順番で、さらに「伊勢エビのような大きなエビ(Robster)をいれると「Robster > Prawn > Shripm」の順番になります。
スポンサーリンク
ところで海老・蝦の違いは?
すっかり放置されていた海老と蝦の違い。
エビという漢字は「海老」と「蝦」以外にも螧、魵、蛯などがあり、それらも同じ「エビ」でありながら、意味が少し違います。
その違いというのが偶然なのか、それとも何か繋がりがあるのか、「Lobster > Prawn > Shrimp」と同じ分かれ方をしています。
Lobsterなど大型のエビを「海老」
Prawnにあたる中型のエビで歩行できるエビが「螧」や「蛯」
そしてShrimpにあたる水中を泳ぐのが「蝦」「魵」「鰕」というそうです。
まとめ:Shrimp・Prawn・海老・蝦の違い
いろいろ書いていきましたが、学術的な違いを抜きにして日常生活に直結するShrimp・Prawn、そして海老と蝦の違いは「サイズ」のようです。
- 大 … 海老 Robster
- 中 … 螧・蛯 Prawn
- 小 … 蝦 魵 鰕 Shrimp
ちなみにこの漢字や英語の使い分けは厳密ではありません。
漢字の場合、日本人だって区別が出来ない人がほとんどですよね。それに「海老」以外の漢字は、日常的に使われないことも多いので「海老」と表記しても問題なさそうです。